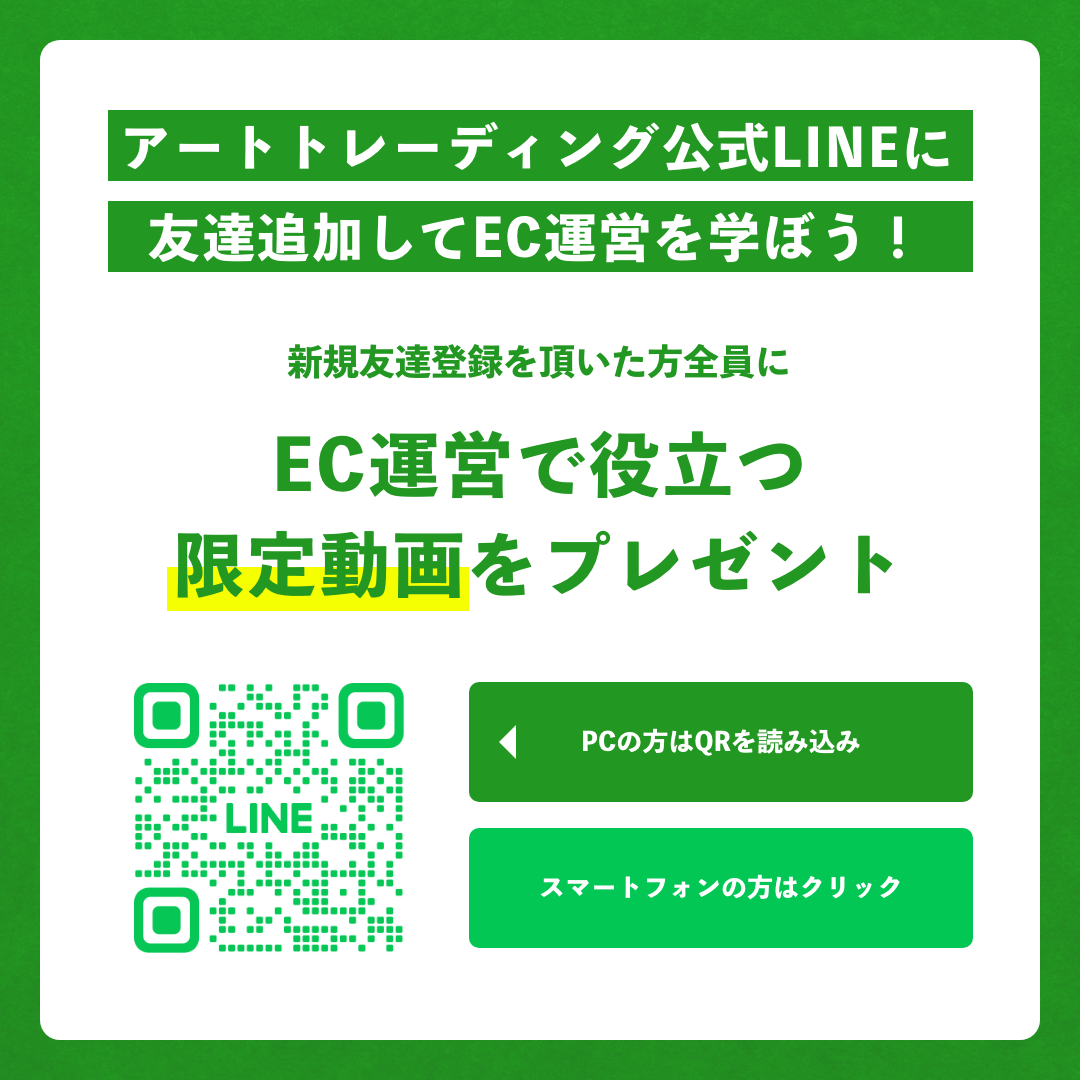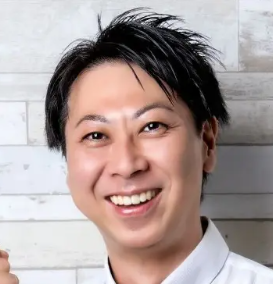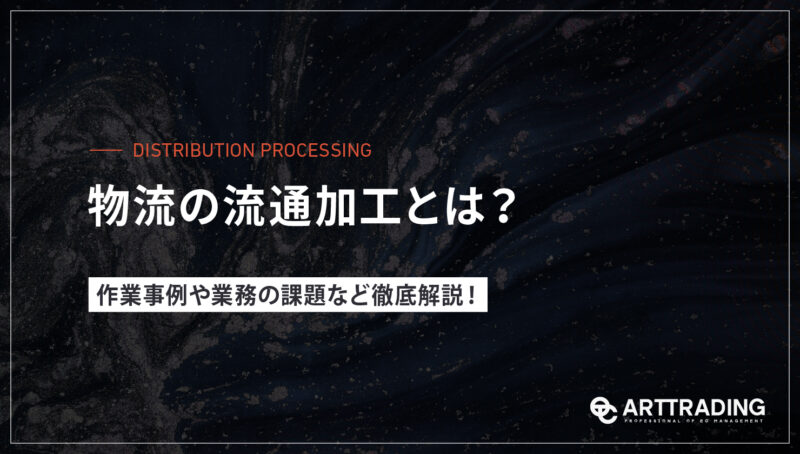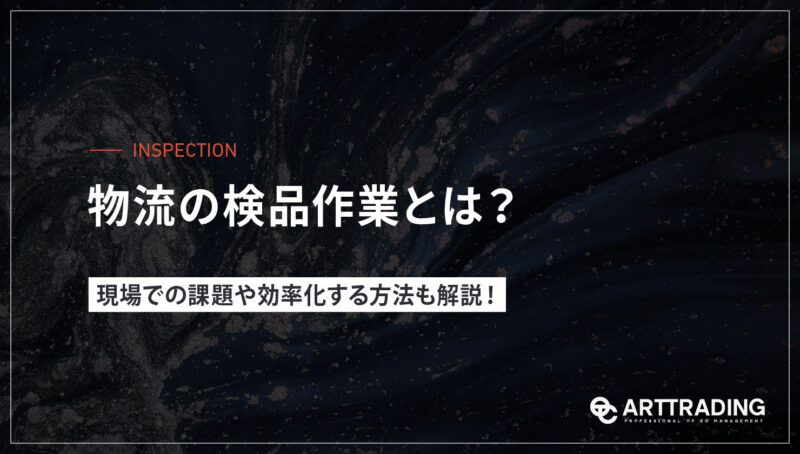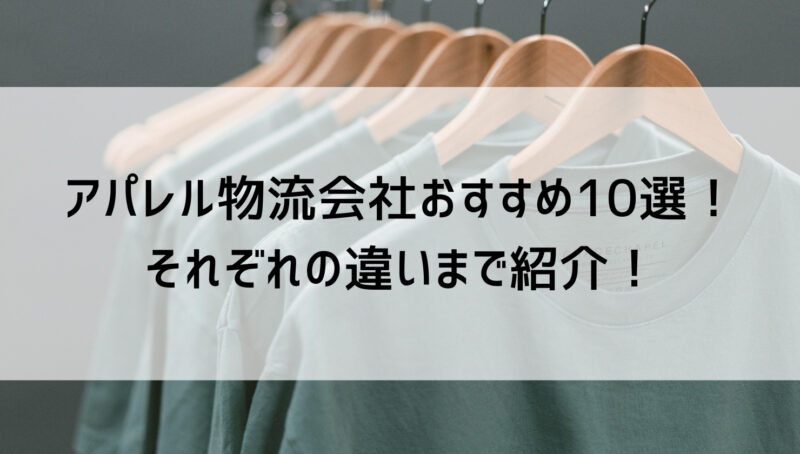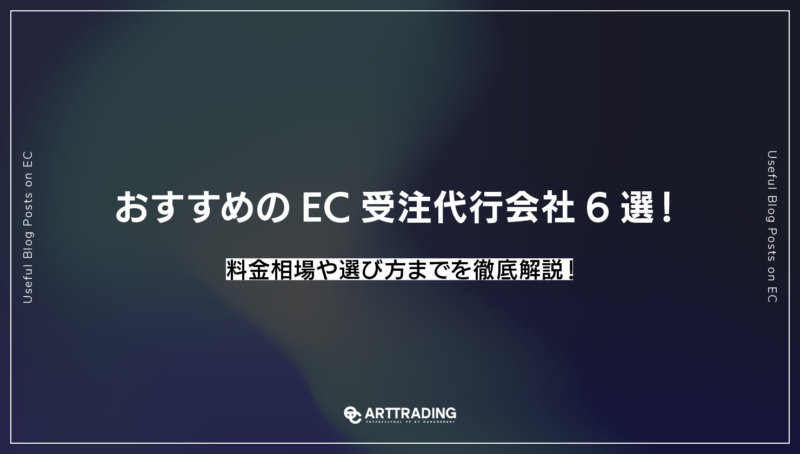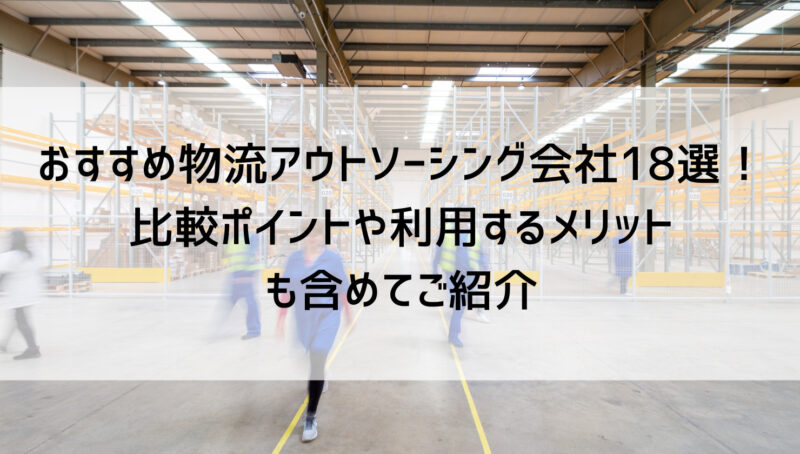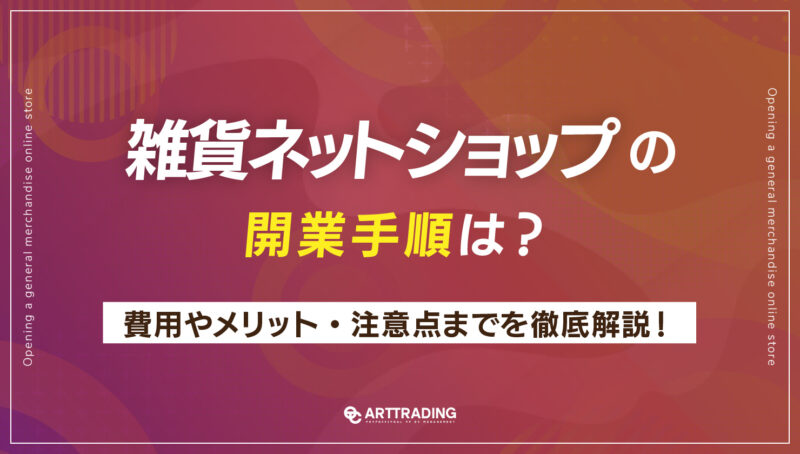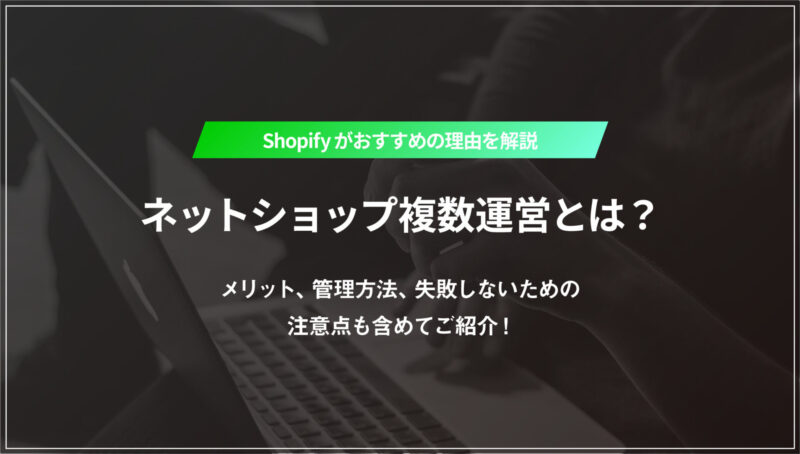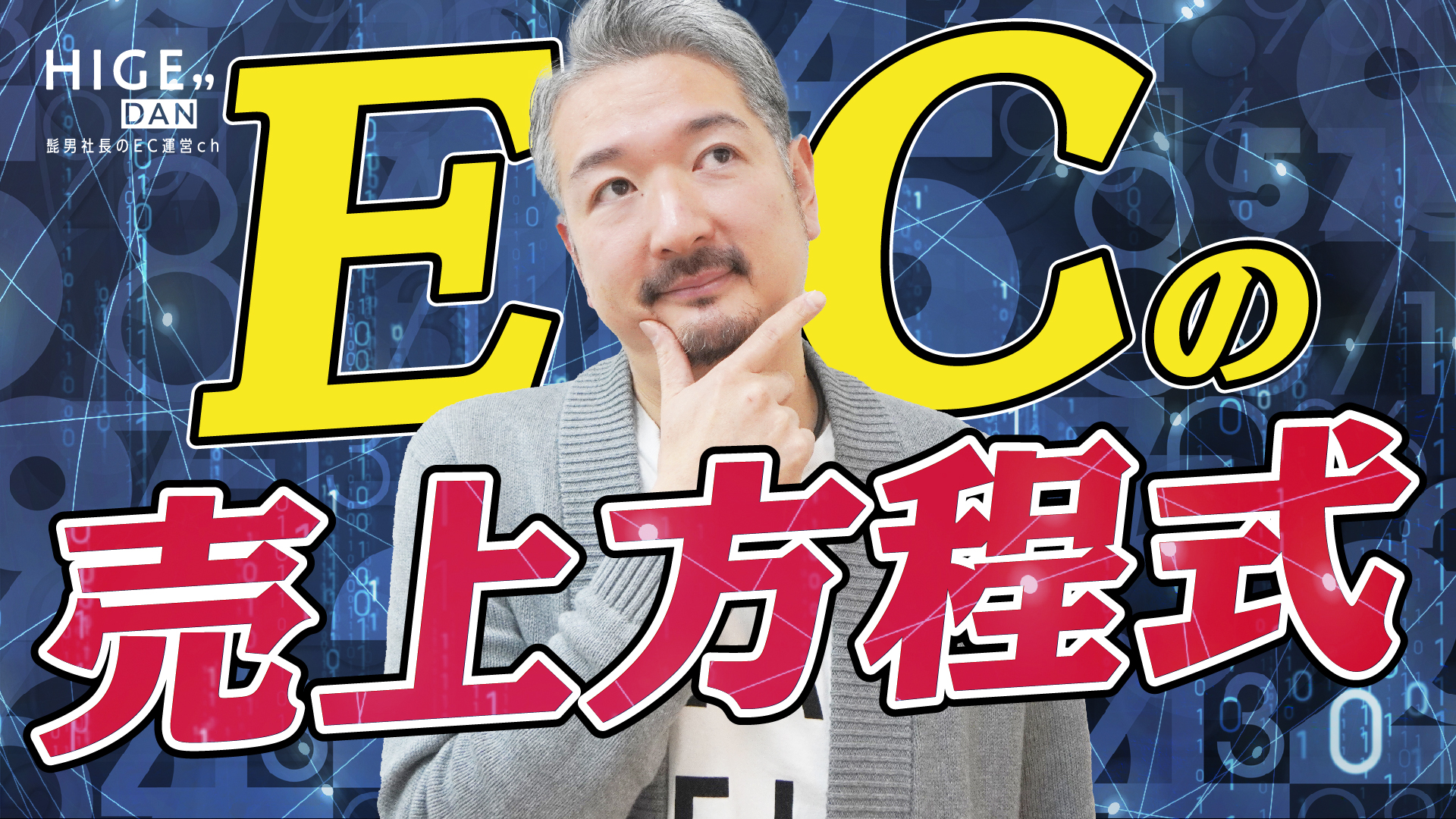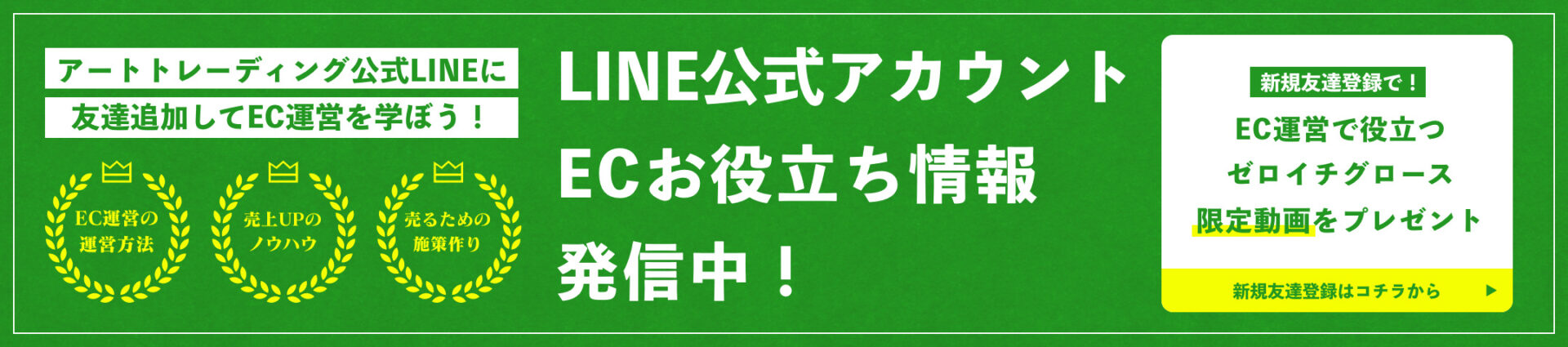EC物流倉庫の特徴とは?おすすめの4社や選定ポイントも解説!
EC物流倉庫の特徴とは?おすすめのEC物流倉庫はどこ?と気になっていませんか。
EC物流倉庫とは、オンラインで注文された商品を保管、管理し、迅速に出荷するための施設のこと。
また物流業務を委託する際におすすめのEC物流倉庫は、以下の4社です。
・アートトレーディング株式会社
・株式会社エスグロー
・株式会社三協
・株式会社テスココンポ
この記事ではEC物流倉庫の特長や委託する際の選び方、自社でEC物流倉庫を立ち上げる際のステップなど、EC物流倉庫について詳しく解説していきます。
是非参考にしてくださいね。
目次
・EC物流倉庫とは?・おすすめのEC物流倉庫4選・EC物流倉庫の特長とは?・どういったEC物流倉庫を利用すればいい?・EC物流倉庫を利用するメリット・EC物流倉庫を利用するデメリット・EC物流倉庫の種類・EC物流倉庫に求められること ・EC物流倉庫を自社で立ち上げる際のステップ・まとめ
EC物流倉庫とは?
EC物流倉庫とは、ECサイトで販売している商品を保管し、注文に基づいて商品をピッキング、梱包、出荷するための施設です。
EC物流倉庫では、オンラインでの購入が行われた後、迅速かつ効率的に商品を顧客に届けます。また倉庫によっては、在庫管理、注文処理、返品対応などの対応も受け付けているので、委託することでEC事業の物流をスムーズに行うことが可能になります。
おすすめのEC物流倉庫4選
ECの物流倉庫におすすめの代行会社は、以下の4社になります。
・アートトレーディング株式会社
・株式会社エスグロー
・株式会社三協
・株式会社テスココンポ
それぞれ見ていきましょう。
アートトレーディング株式会社

| 会社名 | アートトレーディング 株式会社 |
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 20F |
| 電話番号 | 03-5422-3348 |
| 設立年 | 1996年1月12日 |
◆おすすめポイント
アートトレーディング株式会社は、埼玉所沢にフルフィルメントセンターをもつEC物流倉庫です。
一番の特長は、大量出荷から小ロットの出荷まで対応しているので、大手企業から個人の方まで幅広く依頼を受け付けていること。
また、入荷から出荷などの物流業務以外にも、受注業務やカスタマーサポート、商品のささげ業務(撮影・採寸・原稿作成)までを一貫して対応することが可能です。
物流業務においては、商品のギフトラッピングやカタログ、サンプルなどの同梱作業にも柔軟に対応できます。さらに、毎月開催される物流ミーティングでは、事業者にとって最適な提案を受けることができるため、物流業務を安心して委ねることが可能です。
アートトレーディング株式会社
株式会社エスグロー

| 会社名 | 株式会社エスグロー |
| 所在地 | 神戸市中央区琴ノ緒町2丁目2番1号 三経イーストビル 3階 |
| 電話番号 | 078-291-6459 |
| 設立年 | 平成7年8月20日 |
◆おすすめポイント
株式会社エスグローは、兵庫県神戸市にあるEC物流倉庫。
一番の強みは、即日出荷・翌日お届けが可能であること。また出荷精度99.98%の高品質物流が可能なので、クレーム低減により顧客満足度アップが可能です。
さらにエスグローは海外スタッフも在籍しているため、多言語対応が必要な越境EC物流の依頼をうけることもできます。
株式会社三協

| 会社名 | 株式会社三協 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市今米1-15-11 |
| 電話番号 | 072-967-6010 |
| 設立年 | 昭和43年(1968年) |
◆おすすめポイント
株式会社三協は大阪府東大阪市にあるEC物流倉庫。
一番の強みは、本社と8つの拠点が大阪に位置していること。そのため関西地方へのサービス提供に強みを持っていると言えるでしょう。
また物流倉庫の見学会や物流に関するセミナーなども実施しているため、事前に倉庫の雰囲気をつかむことができ安心です。
株式会社テスココンポ

| 会社名 | 株式会社テスココンポ |
| 所在地 | 〒361-0056 埼玉県行田市持田2165 |
| 電話番号 | 048-550-2141 |
| 設立年 | 昭和40年(1965年)6月 |
◆おすすめポイント
テスココンポ株式会社は、埼玉県行田市にあるEC物流倉庫。
一番の強みは、BtoCだけではなくBtoBへの物流にも精通している所。大手GMSの共同配送認定も受けているため信頼して業務を委託することができるでしょう。
また物流業務では、タグ発行やハンガー付けなどさまざまな付帯作業にも対応している点も魅力の1つです。
EC物流倉庫の特長とは?
EC物流倉庫、独自の特長は、以下の通りです。
・ピッキングの頻度が多い
・SKUが多い
・迅速な出荷が必要
・リターン対応が必要
・シーズン性がある
・フレキシブルなスペースが必要
それぞれ見ていきましょう。
ピッキングの頻度が多い
EC物流倉庫の特長として、倉庫でのピッキングの頻度が多いということが挙げられます。
その理由について以下で見ていきましょう。
◆多様な商品の取り扱い
EC物流倉庫では、さまざまな種類の商品を取り扱います。消費者はオンラインで幅広い商品から選ぶことができるため、それぞれの商品に対するピッキングの頻度が高まります。
例えば、あるEC物流倉庫が衣服、電子製品、家庭用品、食品など幅広いカテゴリーの商品を扱っているとします。顧客Aは新しいスマートフォンを、顧客Bはキッチン用品を、顧客Cは最新のファッションアイテムをそれぞれ注文します。このように多様な商品が一つの倉庫から出荷されるため、さまざまな商品に対するピッキング作業が頻繁に発生するというわけです。
◆小規模注文の増加
オンラインショッピングの利便性により、顧客は以前よりも頻繁に、少量の商品を注文するようになりました。
例えば、顧客が一週間に数回、それぞれ異なる日に1-2点の商品を注文する場合、これらの小規模な注文が集まると、倉庫では一日に何百ものピッキング作業が必要になります。
◆迅速な配送が必要
オンラインショッピングでは「翌日配送」や「即日配送」など、迅速な配送が常に期待されています。例えば顧客は午前中に注文した商品を、その日の午後や翌日には受け取りたいと考えるため、倉庫では複数の注文を受けてから一気にピッキング作業を行うのではなく、注文を受けるたびに頻繁にピッキング作業を行う必要があります。
SKUが多い
EC物流倉庫の特長2つ目はSKUが多いということ。SKUとは、それぞれの商品を区別するための番号やバーコードのことです。例えば、違う色やサイズのTシャツがそれぞれ異なるSKUを持ちます。
SKUが多い場合、具体的にどういったことが必要になるのか以下で見ていきましょう。
◆在庫管理システムの導入
SKUが多い場合、それぞれの商品の在庫管理が複雑になります。そのため、在庫管理を効率化するため在庫管理システムの導入が必要になるでしょう。
在庫管理システムを導入しない場合、特にSKUが多いEC物流倉庫においては様々な問題が生じる可能性があります。
例えば、倉庫で何千もの異なる衣類アイテムを扱っているとすると、各アイテムのサイズや色ごとの在庫状況を手動で常に更新し続けるのはほぼ不可能ですし、在庫過剰や不足が生じやすくなります。
そのため、効率的な在庫管理システムの導入は、EC物流倉庫には必要不可欠と言えるでしょう。
◆在庫管理の課題
SKUが多い場合、在庫過剰や品切れなどのリスクも増えます。適切な在庫レベルを維持するためには、精密な需要予測と在庫調整が求められます。
例えば、人気が急上昇している特定のファッションアイテムがあるとします。このアイテムの需要を正確に予測しなければ、在庫不足による売上機会の損失、または在庫過剰による不要な保管コストが発生する可能性があります。多様なSKUを持つ倉庫では、このようなバランスを取ることが特に重要です。
◆物流の最適化
SKUの多いと、ピッキングやパッキング作業の効率が悪くなってしまう場合があります。そのため、各商品の特性に合わせて物流プロセスを最適化する必要があると言えるでしょう。例えば、「商品の大きさ、形状、重量に応じて倉庫の配置場所を変更する」「商品に合わせて異なるピッキング戦略を採用する」といったように、取り扱い商材に合わせて工夫する必要があります。
迅速な出荷が必要
EC物流倉庫の特長として迅速な出荷が必要ということが挙げられます。
というのもEC市場では、迅速な商品の配送もEC運営成功のカギとなるからです。
それでは、以下でなぜEC物流倉庫で迅速な出荷が必要なのかを詳しく解説していきます。
◆顧客の期待が変化しているから
近年、オンラインショッピングの顧客は、注文した商品をできるだけ早く受け取りたいと考えている方が多いです。
そのため、配送の速さが購入決定の後押しになるケースも多いと言えるでしょう。このニーズに応える、EC物流倉庫は注文された商品を迅速に処理し、出荷する必要があります。
◆競争よりも優位なサービスを提供するため
迅速な出荷は、競争が激しいEC市場において、他社との差別化を図る手段となります。
例えば、同じ商品を扱っている他のオンラインストアよりも速く商品を顧客に届けることができれば、顧客のリピート率やロイヤルティの向上につながります。
リターン対応が必要
オンラインショッピングでは、顧客は商品を直接試すことができません。そのため、購入後に商品が期待通りでない場合、返品や交換を求められる場合があります。EC物流倉庫は、このようなリターン対応を効率的かつ迅速に処理する必要があると言えるでしょう。
それではリターン対応において必要なことは何か、以降で解説していきます。
◆返品プロセスの最適化
返品の処理では、商品が返品されたタイミングで、物流倉庫側がその商品の状態を検査し、再販できるかどうかを判断しなければなりません。
そのためこの作業を効率化するために返品処理システムの導入が必要であるといるでしょう。
◆在庫管理の調整
返品された商品が在庫に再び入れられる場合、在庫管理システムに商品が再販可能な状態であることを更新しなければなりません。この返品処理が遅れると、在庫数を正確に把握することができず、売り逃しのリスクが高まるでしょう。
◆コスト管理
リターン対応は、返品された商品の検査、再梱包、再出荷など時間とリソースがかかります。そのため物流倉庫では、これらのプロセスを効率化し、コストを最小限に抑える必要があると言えるでしょう。
シーズン性がある
EC物流倉庫の特長として、シーズン性があるということが挙げられます。
つまりEC物流倉庫では、季節や特定のイベントによって商品の出入りが大きく変わるということです。以降ではこのシーズン性の影響について詳しく見ていきましょう。
◆需要の変動がある
EC物流倉庫では、特定の季節や祝日には、特定の商品の需要が急増します。そのため、これらの期間に需要が高まる商品の在庫を増やす必要があります。
◆物流プロセスの調整
高需要期には、出荷量の増加に対応するための物流プロセスの調整が必要です。
迅速なピッキング、梱包、配送を行うため、人員追加の必要性も出てくるでしょう。
フレキシブルなスペースが必要
EC物流倉庫では、ECサイトの需要の変動や商品の多様性に柔軟に対応するためフレキシブルなスペースが必要になります。
具体的にどういうことなのか、以降で見ていきましょう。
◆需要の変動に対応
ECサイトでは、プロモーション、祝日、季節の変化によって、物流の需要が大きく変動します。
倉庫スペースに余裕をもつことで、需要の変動に応じて、商品を適切なスペースに配置することができ、在庫の回転率を高めることができます。
◆商品の多様性
EC物流倉庫では、さまざまな種類の商品を扱います。商品によってサイズ、形状、保管条件が異なるため、異なるタイプの保管スペースが必要です。
◆拡張性
ECサイトの成長に伴い、物流倉庫は将来的な商品ラインの拡張に対応できる必要があります。倉庫に余裕があれば、ビジネスの成長に伴い必要なスペースを柔軟に確保することが可能です。
どういったEC物流倉庫を利用すればいい?
EC物流倉庫に委託する際、以下のような特徴を持つ倉庫に依頼するのがおすすめです。
・自社に合った設備を持っている
・妥当な料金体系である
・ロケーションが良い
・柔軟性がある
・最新のシステムを導入している
・評判や実績が良い
・コミュニケーションがスムーズである
それぞれ見ていきましょう。
自社に合った設備を持っている
EC物流倉庫のアウトソーシングを考える場合、まずは「自社に合った設備をもっている倉庫」を選ぶようにしましょう。
というのも、ECサイトで取り扱う商品によって、物流倉庫に必要な設備は様々だから。
以降では、取扱商品のジャンル別にどういった設備が必要なのかを見ていきましょう。
◆食品
食品を扱う場合、新鮮さを保つための冷蔵・冷凍設備が完備された物流倉庫が必要です。食品安全規格に準拠しているかも重要です。例えば、冷凍フードや新鮮な果物を扱う企業は、温度管理が徹底された物流倉庫を選ぶ必要があります。
◆医薬品
医薬品を扱う場合、厳格な温度管理と清潔な保管環境が求められます。特定の医薬品は特定の温度で保管する必要があり、そのための設備が整っている物流倉庫が適しています。医薬品の取り扱いに関する規制への準拠も重要です。
◆化粧品
化粧品の場合、品質を維持するための温度管理や湿度管理が重要です。特定の化粧品は直射日光や高温を避けて保管する必要があるため、これらの条件を満たす物流倉庫を選ぶ必要があります。
◆電子機器
電子機器を扱う場合、静電気や湿度のコントロールが重要です。高価値の商品を扱うため、セキュリティ対策がしっかりとされている物流倉庫が望ましいです。例えば、スマートフォンやコンピューター部品を扱う企業は、これらの要件を満たす倉庫を選ぶ必要があります。
◆大型・重量物(家具、機械類など)
頑丈な棚やクレーン、フォークリフトなどの重量物を扱うための設備が必要です。大型商品の安全な保管と移動に適したスペースが必須です。大型商品の組み立てや梱包、特別な配送手配が可能なサービスが望ましいです。
妥当な料金体系である
EC物流倉庫を利用する場合、代行料金が妥当な料金体系であるかも確認するようにしましょう。
物流倉庫の料金体系は様々ですが、以降では一般的に物流倉庫でかかる料金とその相場について紹介していくので、参考にしてくださいね。
◆保管料金
商品を倉庫に保管するための料金で、通常は保管スペースの大きさや使用する棚の数で計算されます。相場は月額数千円から数万円で、小規模なスペースであれば月額5,000円から10,000円程度、大きなスペースでは月額数万円になることもあります。
◆ピッキング料金
商品を倉庫から取り出し、注文ごとに準備する作業の料金です。相場は1アイテムあたり20円から100円程度で、大量注文や特殊な取り扱いが必要な商品では料金が高くなることがあります。
◆梱包料金
商品を梱包するための料金で、使用する梱包材の種類や大きさによって異なります。相場は1梱包あたり50円から数百円で、特別な梱包材を使用する場合や大型商品の場合はそれ以上になることがあります。
◆配送料金
商品を顧客に配送するための料金で、距離や商品の重さ、サイズ、配送スピードによって異なります。相場は配送先やサイズにより異なりますが、小型の標準的な荷物であれば国内の場合は数百円から1,000円程度が一般的です。
◆返品処理料金
返品された商品の処理にかかる料金です。相場は商品や処理の内容によって異なりますが、1件あたり数百円から数千円程度が一般的です。
ロケーションが良い
EC物流倉庫を選ぶ際、ロケーションが良いかという点も確認するようにしましょう。
倉庫のロケーションについては、以降で紹介する点をチェックしておいてください。
◆主要な交通網へのアクセス
消費者が商品を購入後、できるだけ早く商品を届けられるようにしていきたいという場合は、主要な交通網へのアクセスが近い倉庫を選びましょう。
というのも倉庫が主要な高速道路、鉄道線、空港などに近い場合、製品の迅速な配送が可能になるから。
都市部に近い物流倉庫は、配送時間を短縮し、より多くの顧客に迅速にサービスを提供できるでしょう。
◆供給元や市場への近さ
製品の供給元や主要な市場に近い倉庫を選ぶことで、輸送コストを削減し、供給チェーンの効率を向上させることができます。
例えば、製造工場や主要な流通センターに近い倉庫を選べば、在庫補充の時間とコストを削減することが可能です。
◆顧客ベースの地理的位置
企業の主要な顧客基盤が特定の地域に集中している場合、その地域に近い倉庫を選ぶことで、顧客への配送時間を短縮し、顧客満足度を高めることが可能です。例えば、東京都内に多くの顧客を持つECサイトは、関東地方に位置する物流倉庫を選ぶことが望ましいでしょう。
柔軟性がある
EC物流倉庫を選ぶ際に、その倉庫に柔軟性があるかという点も確認しておきましょう。
というのもフレキシブルなスペースが必要でも紹介したように、EC物流倉庫では季節やタイミングによって物流作業の需要が増減します。
具体的にどういうことなのか、詳しく見ていきましょう。
◆需要の変動への対応が可能か
オンライン小売業者が期間限定のセールを行う場合、短期間で大量の注文が発生する可能性があります。そのため、このような一時的な需要の増加に迅速に対応し、追加の在庫保管スペースや増員などを確保できるEC物流倉庫を利用するようにしましょう。
◆シーズン商品の取り扱い
アパレル企業が季節ごとのコレクションを販売する場合、夏用の商品や冬用の商品など、シーズンによって取り扱う商品が異なります。そのため、これらの季節ごとの商品変更に対応し、必要に応じて保管スペースを調整できる物流倉庫に依頼するのがベストでしょう。
◆ビジネスの成長に伴うスケールアップ
EC運営を行う場合、新しい市場に進出したり、商品ラインを拡充する場合があり、その度に物流のニーズが変化します。
そのためEC物流倉庫を選ぶ際は、拡張可能な保管スペースや多様な物流サービスを提供している倉庫を選ぶのが望ましいでしょう。
最新のシステムを導入している
EC物流倉庫を選ぶ際は「最新のシステムを導入しているか」という点も確認しましょう。
下記でどんなシステムがあるのかを紹介していきますが、特に重要なのが「リアルタイム在庫管理システム」を導入しているかという点になります。
それ以降のシステムを利用しているEC物流倉庫は、利用コストが上がる可能性もあるので、費用感を考慮して選ぶようにしましょう。
◆リアルタイム在庫管理システム
最新の在庫管理システムを備えた物流倉庫は、在庫の正確な追跡と管理をリアルタイムで行うことができます。これにより、在庫過剰や不足を避け、必要な時に適切な補充が可能になります。
◆自動化ピッキングシステム
自動化されたピッキングシステムやロボットを導入している物流倉庫は、人手によるピッキングよりも速度と正確性を大幅に向上させることができます。これにより、注文処理時間の短縮とヒューマンエラーの低減が可能になります。
◆先進的な梱包技術
自動化された梱包ラインやエコフレンドリーな梱包材を使用することで、梱包プロセスの効率化と環境への配慮が実現できます。
評判や実績が良い
EC物流倉庫を選ぶ際は、評判や実績についても確認しておきましょう。
以降では、評判や実績についての確認方法を紹介していきます。
◆ネット上のレビューをチェック
インターネット上でのレビューや評価を確認します。Googleマップや業界専門のサイト、ビジネスフォーラムなどでのレビューが参考になります。顧客の体験談や評価から、サービスの品質や顧客満足度を把握しましょう。
◆ホームページでの事例確認
物流倉庫のウェブサイトで、成功事例やケーススタディを探します。事例紹介から、倉庫がどのような業界の物流を得意とし、どの程度の効率化を実現したかを確認しましょう。
◆SNSなどで業界関係者に確認
業界関係者やビジネスパートナーからSNSなどで直接評判を確認するという方法です。少しハードルは高いですが、実際の利用者の意見は、公開されている情報よりも信頼性が高いでしょう。
◆倉庫に訪問する
可能であれば、物流倉庫を直接訪問し、オペレーションを見学します。実際に倉庫の運営を目の当たりにすることで、その効率性や組織の管理能力を直接確認できます。
コミュニケーションがスムーズである
EC物流倉庫を選ぶ際は、担当者とのコミュニケーションがスムーズであるかも確認しておきましょう。
というのも、物流作業を代行してもらう上でコミュニケーションがスムーズでないと、日常の業務運営はもちろん、緊急時に自社のEC運営の信頼性を下げることになってしまいます。
それではどうやって「コミュニケーションがスムーズにとれるか」を確認するべきなのか、以降で紹介していきます。
◆初期の問い合わせ対応をチェックする
物流倉庫に初めて問い合わせをした際の対応をチェックします。
返信の速度、問い合わせに対する答えの明確さ、対応の丁寧さなどを確認するようにしましょう。
◆参考訪問時のコミュニケーションを観察する
可能であれば、物流倉庫を訪問して、スタッフとの直接コミュニケーションを取るようにしましょう。対面でのやり取りから、スタッフの専門性や対応力を確認できます。
◆コミュニケーションチャネルの多様性を確認する
倉庫がどのようなコミュニケーションチャネル(電話、メール、チャットサービスなど)を提供しているかを確認しましょう。複数のチャネルが利用可能であれば、異なる状況に応じた柔軟なコミュニケーションが可能です。
EC物流倉庫を利用するメリット
EC物流倉庫を利用するメリットは、以下の通りです。
・在庫管理の効率化ができる
・コスト削減
・ビジネスの拡張が柔軟にできる
・顧客サービスが向上する
それぞれ解説していきます。
在庫管理の効率化ができる
EC物流倉庫では、在庫がリアルタイムで追跡され、自動化された在庫管理システムが利用されることが多いです。例えば、商品が低在庫になると自動で発注するシステムがあり、在庫切れによる販売機会の損失を防げます。
コスト削減
物流倉庫を利用することで、自社で倉庫を運営するコスト(人件費、設備投資、維持管理費等)を削減できます。たとえば、季節ごとの需要の変動に対応して柔軟にスペースを調整できるため、無駄なスペースコストを削減できます。
ビジネスの拡張が柔軟にできる
ビジネスが拡大するにつれて、物流倉庫のサービスを拡張することが可能です。例えば、ビジネスが成長し商品ラインナップが増えた場合でも、追加の在庫スペースやリソースを柔軟に利用できます。
顧客サービスが向上する
迅速な配送や正確な在庫管理により、顧客満足度を高めることができます。例えば、配送状況をリアルタイムで追跡できるシステムを利用し、顧客に対して透明かつ正確な情報を提供することが可能です。
EC物流倉庫を利用するデメリット
EC物流倉庫を利用するデメリットは、以下の通りです。
・細部のコントロールができなくなる
・サービスの質にばらつきがある
・情報共有が難しい
・依存度の増加
それぞれ解説していきます。
細部のコントロールができなくなる
自社で物流を管理しない場合、運営の細部に対するコントロールができなくなるというデメリットがあります。例えば、倉庫の従業員が商品を適切に取り扱わない場合、直接介入して指導することが難しいでしょう。
サービスの質にばらつきがある
物流業者によってサービスの質が異なり、一貫したサービスを提供することが難しい場合があります。例えば、ある物流業者は迅速な配送を行う一方で、別の業者は配送に時間がかかる可能性があります。
情報共有が難しい
EC物流代行を利用するデメリットとして、代行を依頼している物流会社との情報共有が難しくなるということが挙げられるでしょう。例えば、在庫データや配送状況をリアルタイムで把握するためには、物流業者との間で効果的なコミュニケーションとシステムの整合性が必要です。
依存度の増加
物流業者に出荷作業を依頼することで、その業者の問題が自社のビジネスに直接影響を及ぼすリスクがあります。例えば、自然災害により委託会社がサービスを提供できなくなると、自社の商品配送に大きな支障をきたす可能性があります。
EC物流倉庫の種類
EC物流倉庫には、利用用途や商品に合わせていくつか種類があります。
・3PL倉庫
・フルフィルメントセンター
・クロスドッキングセンター
・冷蔵、冷凍倉庫
・危険物倉庫
・自動化倉庫
それぞれ詳しく解説していきます。
3PL倉庫
3PL倉庫とは、物流業務を代行する業者が運営する倉庫のことです。
「物流」とは、荷物を運ぶこと、倉庫での保管、荷造りや加工、トラックへの積み込みや積み下ろしを含む、商品の移動に関わる一連の作業のことで、3PL倉庫ではこれらの作業を代行して行ってくれます。
また倉庫によっては、流通加工などの作業も請け負ってくれる場合もあるので、自社のニーズに合った設備を整えている倉庫に依頼するようにしましょう。
◆3PLサービスが適しているのはどんなEC事業者?
3PLサービスは、以下のようなEC事業者におすすめです。
事業の拡大に伴い、より複雑な物流ニーズに対応する必要がある大規模事業者にとって、3PLは物流の効率化とスケールアップをサポートします。
・多様な商品や国際的な事業を行っている事業者
3PLは多くの商品カテゴリーや国際的な配送ニーズを持つ事業者にとって、柔軟な物流ソリューションを提供し、複雑なサプライチェーンの管理をサポートします。
フルフィルメントセンター
フルフィルメントセンターは、物流業務に加えて、顧客の注文処理、コールセンター業務、さらには決済処理をも含むよりEC運営に必要なすべてのバックヤードサービスを提供しています。
3PLが提供する物流業務だけではなく、注文処理やコールセンターなどの顧客対応も代行することができるため、委託すれば、よりEC運営におけるコア業務に集中することが可能です。
◆フルフィルメントサービスが適しているのはどんなEC事業者?
フルフィルメントサービスは、以下のようなEC事業者におすすめです。
フルフィルメントセンターは、顧客との直接的なコミュニケーションが必要な事業者にとっておすすめのサービスです。
フルフィルメントセンターは、注文処理から配送、顧客対応までの一連のプロセスをスムーズに行い、顧客の期待に応えるサービスを提供するため、顧客満足度向上に寄与することができるでしょう。
・スケールアップを目指す中小規模のEC事業者
フルフィルメントセンターは物流だけでなく、顧客対応、決済処理のスムーズな運営を支援し、ビジネスの拡大をサポートします。特にリソースが限られている中小規模のEC事業者にとって、フルフィルメントセンターを利用することで、コア業務に集中することができ、効率的に事業を成長させることができるでしょう。
クロスドッキングセンター
クロスドッキングとは、入荷した貨物を在庫として保管することなく、すぐに仕分けを行い、出荷へと移行する物流の仕組みのこと。
クロスドッキングセンターとは、この仕分け作業を行う施設のことで、さまざまな方面からの貨物を迅速に処理し、次の目的地へと転送します。
クロスドッキングを採用することにより、従来の倉庫業務で必要とされる長期的な商品保管や保管に伴う複雑な管理作業が不要になり、物流プロセスの簡素化が可能。これにより、配送時間が短縮され誤送や損傷のリスクが減少するというメリットがあります。
◆クロスドッキングに適しているのはどんなEC事業者?
クロスドッキングに適しているのは、以下のようなEC事業者です。
食品やファッションなど、迅速な在庫回転が必要な業界の事業者に適しています。
・多品種少量配送を行う事業者
小ロットで多様な商品を取り扱う事業者にとって、クロスドッキング施設は効率的な物流プロセスを提供します。
・需要予測が難しい事業者
需要の変動が激しい事業者にとって、在庫を最小限に抑えるクロスドッキングはリスク管理に有効です。
冷蔵・冷凍倉庫
冷蔵・冷凍倉庫は、特定の温度管理が必要な商品の保管に特化したEC物流倉庫です。
冷蔵・冷凍倉庫は、温度に敏感な商品を扱う際の品質維持、安全性確保、法規遵守といった複数の重要な側面を兼ね備えています。
◆冷蔵・冷凍倉庫の利用に適しているのはどんなEC事業者?
冷蔵・冷凍倉庫を利用するべきEC事業者は、以下の通りです。
新鮮な食品や冷凍食品を取り扱うEC事業者にとって、冷蔵・冷凍倉庫は商品の鮮度を維持する上で不可欠です。
・医薬品業界
特定の温度で保管する必要がある医薬品やバイオテクノロジー製品を扱う事業者にとっても、これらの倉庫は品質保持の重要な要素です。
・化粧品業界
一部の化粧品やスキンケア製品は、品質を保つために特定の温度で保管する必要があります。これに対応するためにも、冷蔵・冷凍倉庫が有効です。
危険物倉庫
危険物倉庫は、特に危険性を持つ物資、例えば化学物質、爆発物、可燃性物質などを安全に保管するための専門的な倉庫です。
この倉庫は、特別な建築基準や安全規定に基づいて設計されており、火災、爆発、化学物質の漏洩などのリスクを防ぐために厳格な安全措置が講じられています。
また、危険物倉庫は、適切な換気システム、火災警報装置、消火設備などを備え、常に緊急事態に対応できる体制を整えています。さらに、法規制の遵守を非常に重視しており、特定の危険物質を取り扱う際の法的な要件を満たすように設計されています。
◆危険物倉庫の利用に適しているのはどんなEC事業者?
危険物倉庫がおすすめのEC事業者は以下の通りです。
・化学製品を取り扱う事業者
・化粧品や特殊塗料などの特定の成分を含む商品を扱う事業者
・医薬品や医療機器を扱う事業者
・自動車部品や電子機器など、特定の危険物質を含む製品を扱う事業者
・農薬や肥料などの農業関連商品を扱う事業者
これらの事業者は、危険物倉庫を利用することで、安全な保管と法規制への遵守を確実にし、事故リスクを最小限に抑えることができます。また、顧客と社会への信頼性を高めるためにも、危険物倉庫の利用が推奨されます。
自動化倉庫
自動化倉庫は、最先端の自動化技術を活用して、物流プロセスの効率化と精度の向上を実現するEC物流倉庫です。
特徴は、ロボット技術、自動化されたコンベヤーシステム、ソフトウェアとデータ分析ツールなどが積極的に導入されていること。
自動化倉庫を利用するメリットは、人手による作業を最大限減らすことで、物流プロセスの迅速化と誤差の減少が可能になるということです。
また、在庫管理と追跡が自動化されているため、在庫の正確性が高まり、必要な商品を迅速に見つけ出して出荷することが可能となり、顧客満足度向上も期待できるでしょう。
◆自動化倉庫の利用に適しているのはどんなEC事業者?
自動化倉庫がおすすめのEC事業者は以下の通りです。
・大規模な在庫を持つEC事業者
・大量の注文があり迅速な出荷が必要な事業者
・効率的な在庫管理と精度の高い物流を求める事業者
・ピーク時の注文処理能力を強化したい事業者
・人件費の削減や作業効率の向上を目指す事業者
・高いコストをかけられる事業者
これらの事業者は、自動化倉庫を利用することで、注文処理の迅速化、在庫管理の正確性の向上、顧客満足度の向上などが期待できるでしょう。特に、大量の商品を取り扱い、高い作業効率と精度が求められる事業において、自動化倉庫は重要な役割を果たします。
EC物流倉庫に求められること
EC物流倉庫に求められることはどんなことでしょうか?
▼EC物流倉庫に求められること
・迅速な出荷
・正確な在庫管理
・柔軟な対応能力
・返品、交換の対応
・セキュリティ対策
それぞれ見ていきましょう。
迅速な出荷
EC物流倉庫では、注文後の迅速な出荷が求められます。
迅速に出荷を行うことで、顧客満足度が高まり、リピート購入の可能性が増加します。
もし迅速な出荷ができないと、顧客は注文した商品の到着を待たされ、不満を抱く可能性が高くなります。これにより特に競争の激しいEC市場において、顧客離れや売上の減少につながりかねません。
正確な在庫管理
EC物流倉庫では、正確な在庫管理が求められます。
正確な在庫管理とは、実際の在庫量とデータ上の在庫量が一致している状態を保つことです。これにより、過剰在庫や在庫不足を防ぎ、効率的な在庫回転を実現します。
在庫管理が不正確な場合、商品の売り切れや過剰在庫が発生し、売上機会の損失や不必要な保管コストが生じる可能性があります。
柔軟な対応能力
EC物流倉庫では、柔軟な対応能力も求められます。
具体的には、市場の需要変動や顧客の特殊な要望に迅速に対応するなど、状況に応じて柔軟に対応することで、顧客の多様なニーズに合わせたサービスを提供できます。
柔軟性が不足していると、顧客の要望に応えられず、顧客満足度の低下や売り上げ低下につながる可能性があります。
返品・交換の対応
EC物流倉庫では、返品・交換の対応も求められます。顧客からの返品や交換要求に迅速かつ効率的に対応することで、顧客信頼度を維持し、リピーター獲得にもつなげることができるでしょう。
もし返品・交換の処理が遅れると、顧客不満が生じ、ブランドイメージが損なわれる可能性があります。
セキュリティ
EC物流倉庫では、セキュリティ対策として商品や顧客情報の保護を徹底的に行わなければなりません。セキュリティ対策を万全に行うことで、窃盗やデータ漏洩のリスクを減らし、顧客の信頼を得ることができるでしょう。
セキュリティが不十分な場合、商品の損失やデータ漏洩が発生し、法的責任や信頼性の喪失に繋がる可能性があります。
EC物流倉庫を自社で立ち上げる際のステップ
EC物流倉庫を自社で立ち上げる際のステップは、以下の通りです。
1.ビジネスプランの策定
2.立地の選定
3.施設の設計・建設
4.システム導入
5.人員の確保・教育
6.運用プロセスの確立
7.セキュリティ対策
8.継続的な改善
順を追って解説していきます。
ビジネスプランの策定
自社のEC物流倉庫立ち上げにあたり、まずは市場分析、事業の目標設定、予算計画、予想されるリターンなどのビジネスプランを策定します。
また、提供するサービスの種類、ターゲット顧客、競合との差別化戦略なども明確に定義します。
立地の選定
物流倉庫の立地選定は、物流効率やコスト、市場へのアクセスに大きな影響を与えます。そのため、交通の便利さ、労働力の可用性、周辺地域のインフラ、土地や建設コストなどを総合的に考慮して選定しましょう。
また、将来的な事業拡大や市場の変動に柔軟に対応できる立地の選択も頭に入れておきましょう。
施設の設計・建設
倉庫の建設の際には、効率的な物流の流れ、拡張可能性、環境への配慮などを考慮して設計しましょう。
物流プロセスの最適化を目指し、商品の受け入れから保管、出荷までの流れを効率良く設計します。また、耐久性と安全性を考慮した建設計画が重要です。
システム導入
倉庫管理システム(WMS)の導入は、在庫の正確な追跡と管理を可能にします。
また、注文処理システムや物流管理ソフトウェアの導入により、作業の自動化と効率化を図ることも可能です。システムを選ぶ際には、拡張性や将来の技術進化に対応できる柔軟性も考慮しましょう。
人員の確保・教育
適切な人材の確保と徹底したトレーニングは、倉庫運営の成功の鍵です。人材が確保できたら、物流管理、倉庫作業、顧客サービスに関する知識とスキルの向上を図りましょう。
運用プロセスの確立
次に受注処理から在庫管理、出荷、返品処理まで、効率的で確実な運用プロセスの確立を行いましょう。プロセスの標準化と文書化により、作業の一貫性と再現性を保ちます。
また、問題発生時の迅速な対応とリスク管理のためのマニュアルなども用意しましょう。
セキュリティ対策
物理的なセキュリティ対策として、監視カメラの設置やアクセス制御システムの導入が必要です。また、サイバーセキュリティ対策として、データ保護やシステムのセキュリティ強化を行います。これらの対策は、商品と情報の安全を守るために不可欠です。
継続的な改善
運営開始後も、市場の変化や技術の進化に対応するために、継続的な改善を行いましょう。定期的なレビューとフィードバックに基づいてプロセスを見直し、効率化と品質向上を目指します。
まとめ
物流業務を委託する際におすすめのEC物流倉庫は、以下の4社です。
・アートトレーディング株式会社
・株式会社エスグロー
・株式会社三協
・株式会社テスココンポ
EC物流会社を選ぶ際には、以下のポイントを確認するようにしましょう。
・自社に合った設備を持っている
・妥当な料金体系である
・ロケーションが良い
・柔軟性がある
・最新のシステムを導入している
・評判や実績が良い
・コミュニケーションがスムーズである
関連記事
オススメ記事
YOUTUBEチャンネル -髭男社長のEC運営ch-
関連記事
オススメ記事
人気週間ランキング

Shopifyで納品書や領収書を発行するには?ネットショップ運営に必要な書類や、Shopify上での発行・編集方法をまとめました。
2024.06.23👁20.2k
Shopifyの決済方法をご紹介!コンビニ決済・銀行振込・PayPayも!手数料や設定方法についてまとめました。
2024.06.23👁16.3k
ヤフーショッピングへの出店手順とは?出店審査や個人出店、食品の出品も含めて徹底解説!
2024.06.23👁15.7k
Shopifyで配送地域別に送料を設定するには?利用できる配送業者や配送方法、便利なアプリもご紹介!
2024.06.23👁15k
おすすめのEC運営代行会社24選!費用や仕事内容までをまとめてご紹介!
2024.07.09👁14.5k